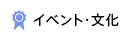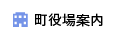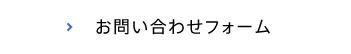出産・子育て
子育て家庭への手当
児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方。なお、受給者は、父母のうち所得の高い方となります。
支給月額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(児童1人あたり) |
|---|---|
| 満3歳未満 | 15,000円(第3子以降:30,000円) |
| 満3歳~高校生年代 | 10,000円(第3子以降:30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
なお、児童の兄姉については、大学生年代(22歳到達年度末)までの兄姉か ら「第1子」として算定しますが、監護している(面倒を看ている)こと、生計が同一である(生活費や学費等を受給者が支出している)ことが要件となります。
「第3子以降」のカウント方法について【こども家庭庁作成】.pdf
支払日
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
なお、支払日が金融機関の休日にあたる日の場合には、直前の営業日に支払います。
| 支給日 | 支給対象月 |
| 2月10日 | 12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
次の方はお手続きが必要となります(事由発生から15日以内にお手続きください)
【認定請求・増額】 ※原則請求月の翌月分からの支給開始となります。
①お子さんが生まれたとき
②他の市町村から転入したとき(請求のみ) 等
【受給消滅】 ※原則届出月までの支給となります。
①他の市町村へ転出したとき
②公務員になったとき 等
※上記のほかにもお手続きが必要な場合がありますので、ご不明な点がございましたらお問い
合わせください。
【現況届】
令和4年度から児童手当の現況届の提出が原則不要になりました。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。対象と思われる方については、町から現況届の書類を送付しますので、期限内にご提出ください。
①DV避難等により住民票登録地と異なる住所の自治体で受給している方
②支給要件児童の戸籍がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④施設対象者、里親等
⑤受給者と児童が別居しており、「別居監護申立書」を提出された方
⑥父母以外が児童の生計維持者となって受給されている方
児童扶養手当
父母の離婚・死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給し、母子家庭・父子家庭等の生活安定を図り、自立を促進することを目的とした制度です。
支給対象
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
①父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
②父(母)が死亡した児童 ※遺族年金が手当額を超える場合には支給されません。
③父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
④母が婚姻によらないで懐胎した児童 等
上記の支給要件に該当しても次のいずれかに該当するときは手当が支給さません。
①受給者や同居している家族に定められた額以上の所得があるとき
②母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
③対象児童を養育、監護しなくなったとき
④対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設や少年院等に入所しているとき 等
申請及び支払日
福祉課 子ども係で申請手続きを行えます。
認定されると、請求月の翌月分から福岡県より支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)の11日にそれぞれ前月分までが支給されます。
なお、支払日が金融機関の休日にあたる日の場合には、直前の営業日に支払われます。
| 支給日 | 支給対象月 |
| 1月11日 | 11月・12月分 |
| 3月11日 | 1月・2月分 |
| 5月11日 | 3月・4月分 |
| 7月11日 | 5月・6月分 |
| 9月11日 | 7月・8月分 |
| 11月11日 | 9月・10月分 |
その他児童扶養手当に関しまして、詳細は福岡県ホームページをご参照ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jidoufuyouteate-23-1.html